今回は国公立医、旧帝大の合格者の実態について書いていきます。
ただし主観的なまとめにはなるので、全てを鵜吞みにはせず、こんな人も受かっているんだと思っていただければ幸いです。
受験勉強をスタートするにあたり、最終的にどれくらい点を取ればいいのかを把握することは非常に重要です。というのも、数学の入試問題って難しすぎるんです!
深堀りしていきます。
一つの大問には(1)から多くても(3)までの設問があり、
(1):肩慣らしで教科書レベルの公式を使って解く問題(難易度としてA)
(2):カモフラージュを剥がし、入試数学の定石を使って解く問題(難易度としてB)
(3):(1)(2)を応用して、定石を複数使って解く問題(難易度としてC)
のように構成されています。
そしてこれらの問題の合格者の点数の取り方として
完答:(1)から(3)までの答えと考え方が合っており、記述で減点がほぼない状態
部分点:(1)(2)は完壁に得点し、(3)は途中まで考え方が合っている状態
があります。
これらを踏まえて、合格者(数学苦手または合格ボーダーすれすれの人)がどのように得点しているかというと、
大問が5題とすると
旧帝大理系(医学部除く):1問完答、3問部分点
国公立医 他学部共通問題あり:他学部共通問題はほぼ完答、医学部専用問題は部分点
医学部専用問題のみ:全て部分点
え、合格者もそんなものなの?って驚いた方も多いかと思います。
初めに書きました。
そう、入試数学って難しすぎるんです!
もちろん、数学が得意な人はもっとバリバリ完答していきますし、上記のような点数で合格していく人は二次試験の英語や理科、共通テストである程度の高得点を取っていることが条件となります。
でもこの実態を知ると、数学だけで医学部、理系を諦めるべきではないんだなと思いますよね。
私ももっと早く教えてもらいたかったです、、笑
私が旧帝大理系に在籍時、聞いてみると数学が全て部分点だったっていう人も何十人といました。
この3回のブログで入試数学の実態をまとめてきましたが、だいぶ全受験生の悪夢「数学」の素性が見えたかなと思います。
次回は、この宿敵との付き合い方を書いていきたいと思います。では!

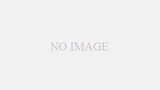
コメント